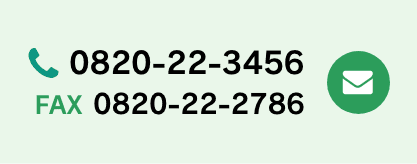勤務医紹介
- 弘本 光幸(診療部長 兼 内科主任部長)
日本内科学会認定内科医・総合内科専門医
日本循環器学会循環器専門医
日本専門医機構認定総合診療専門研修特任指導医 - 沢 映良(循環器内科医師)
日本内科学会認定内科医・内科指導医・総合内科専門医
日本循環器学会循環器専門医
日本心不全、不整脈心電図学会ICD/CRT研修修了
日本専門医機構認定総合診療専門研修特任指導医
- 梶井 俊郎(循環器内科副部長)
日本内科学会認定内科医
日本循環器学会循環器専門医
日本心臓リハビリテーション学会認定心臓リハビリテーション指導士
- 山本 麻紀子(循環器内科医師)
概要
虚血性心疾患、心不全、心原性ショック、不整脈等の循環器疾患に関しての診断から治療まで担当致しております。
- 外来で行う検査及び治療:心エコー、運動負荷心電図、ホルター心電図、心筋シンチグラム、24時間血圧計、血圧脈波検査、末梢血管エコー、24時間経皮的酸素飽和度モニター
- 院で行う検査及び治療:心臓カテーテル検査、心臓電気生理学的検査、冠動脈及び末梢血管の経皮的カテーテル治療、ペースメーカー植え込み、ポリソムノグラフィー(睡眠時無呼吸症候群検査)
- 日本循環器学会より循環器専門医研修施設の認定を受けています。
NCD(一般社団法人 National Clinical Database)の参加について
当院循環器内科は、一般社団法人 National Clinical Databaseが実施しているデータベース事業に参加をしております。この事業は日本全国の参加病院からの診療データを登録し、集計・分析を行う事で医療の質の向上を目指すものです。患者さんにより適切な医療を提供するための専門医の適性配置が検討できるだけでなく、最善の医療を提供するための各臨床現場の取り組みを支援することが可能となります。当科を受診される方は、趣旨をご理解の上、ご協力の程よろしくお願い致します。
登録対象となる患者さんについて
当院循環器内科にて、心臓カテーテル検査等を受けられた方が登録対象になります。登録は患者さんの自由な意思に基づくものであり、参加されたくない場合は、データ登録を拒否して頂く事ができます。なお登録を拒否されたことで、日常の診療等において患者さんが不利益を被ることは一切ございません。
登録される情報の内容について
登録される情報は、日常の診療で行われている検査や治療の契機となった診断、手術等の各種治療やその方法等となります。これらの情報以外の患者さんを容易に特定出来る情報(氏名、住所等)は登録される事はありません。
NCD担当者の訪問による登録データ確認について
当院からNCDへ登録した情報が正しいかどうかを確認するために、NCDの担当者が患者さんのカルテや検査データなどを閲覧する事があります。当院がこの調査に協力する際は、NCDの担当者と守秘義務に関する取り決めを結び、患者さんの個人情報と登録したデータを結びつける事が可能となる情報を院外へ持ち出したり、口外することを禁じます。
|
(249KB) |